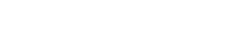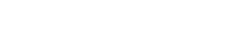トピックス
作業センターふじなみ
秋の保護者ボランティア
2025年10月28日
10月19日(日)に保護者の皆さんのご協力のもと、環境整備を行いました。
夏の間に伸びた雑草の草刈り等をしていただきました。


また、パックセンター前のプランターの植え替えも行いました。

普段手が回らない場所をきれいにしていただき、本当にありがとうございました!
これから年末に向けて椎茸生産は忙しくなります。きれいになった環境で集中して作業に取り組むことができます。
作業センターふじなみ
しいたけ作業一日体験!!
2025年07月25日

特別支援学校の生徒・ご家族を対象に、しいたけ作業一日体験会を実施します。
将来の働く場所をイメージできるよう、ふじなみでの作業や取り組みについて知っていただける内容となっております。
卒業後の進路の参考になればと思いますので、お申込みお待ちしております!!
日時:8月11日(月・祝日) 9:30~11:30
場所:作業センターふじなみ

※参加費は500円ですが、椎茸をお持ち帰りいただけます。
お申込み・問い合わせ先
076-436-7673
担当:室
作業センターふじなみ
今年も真剣に!!
2025年06月18日
 思ったとおり椎茸の生産量が多くならない状況が続いていた。去年の10月、11月くらいには、12月から挽回してやると思っていたけど、思ったどおりにならないまま2024年度が終わってしまった。
思ったとおり椎茸の生産量が多くならない状況が続いていた。去年の10月、11月くらいには、12月から挽回してやると思っていたけど、思ったどおりにならないまま2024年度が終わってしまった。
油断はしてなかったけれど、あんまり守りにばかり入るわけにはいかないから、小さなチャレンジをしながら売上を確保しようとしていたわけだ。気をつけていても、思い通りにならない可能性はある。そして、もちろん思い通りになる可能性もあったというわけだ。これは、毎日シイタケを生産しながら、その時々でベストだと思う選択をしていった結果だったので、品種を「XR1」から「126」にしたのは間違いだったとか、培養日数を短くして回転数を上げたのは間違いだだったとか、培養温度を1℃上げたり、あるいは1℃下げたりするのは間違いだったとか、あれこれ言われても仕方ない。
そして、いま「最適解」がに見つかりつつある。ようやく光が見えてきた。どうやらこれまでよりずっと手応えがある。こんなに手応えがあっても「やっぱり上手くいかなかったかぁ」と思うようなことになる可能性もある。そうならないでほしいのだけれど、ちょっと覚悟もしている。
去年も真剣にやってましたが、今年も真剣です。
いつもシイタケやキクラゲを買いに来てくれてありがとうございます。
シイタケを買いに来てくれる人も、シイタケを作っている人も、みんなが元気で健康に過ごせることを願っています。
ウォーム・ワークやぶなみ
保護者ボランティア
2025年05月13日
5月11日(日)、保護者の皆さんのご協力の下、各事業所周辺の環境整備を行いました。



やねのうえのガチョウでは、清掃・除草作業や店頭に並ぶ鉢植え作りを行いました。
作業センターふじなみでも、清掃・除草作業や花の植え替えを。




ウォームワーク・やぶなみは除草作業と溝掃除を。


みしまの工房では、裏の雑木の伐採と溝掃除を。


金草寮は溝掃除を。
 うさか寮では除草作業などなど・・
うさか寮では除草作業などなど・・


お天気も良く、気持ちの良い汗をかくことが出来ました。
ご協力くださった皆様のお陰で、利用者さん、職員共に気持ちよくお仕事ができます。
本当にありがとうございました!
作業センターふじなみ
環境が大事
2024年09月21日
競争する環境があるとその実力が向上すると思われている。私も、親や先生たちに何度も言われてきて、そういうものなのだろうと思っていた。
競争することで進歩したという物語もたくさんテレビのドキュメンタリーとかで見てきた。
競争相手というライバルがいると強くなるという言い方もある。そういうことは、確かにあるだろうと思うけど、自分がそういう場にいるのは大変だなと、思ってしまう。
だって、自分が向上すれば、競争相手も頑張って向上するってことは、きりがないじゃないかと考えてしまう自分がいた。
できることなら、つらい思いをせずに勝ちたいとか、戦わずして勝つとかのほうがいいような気がする。
勝ちたくないのかと言えば、それは勝ちたい。
ゲームとか試合とか、勝ちたいがなかったらルールも成立しないし、面白くないと、思う。
勝ちたい、向上するのはうれしい、進歩も楽しい。
このことを落ち着いて考えていくと、ますます、競争がいちばんいい方法だとは思えなくなる。
相手より勝つのが競争だとしたら、それは競争相手が失敗したり不運な出来事にあうのも成功である。どんどん相手が弱くなっていったら、競争に勝つためには、こんなにありがたいことはないということになる。
椎茸生産の競争で言えば、ライバルが猛暑で椎茸がうまく育たなかったり、生産者が高齢により作業ができなくなったり、地震や台風などの災害により生産が出来なくなったりすることが考えられるのだろうか。
同様に、こちらとしてもなにかがうまく行くことよりも、失敗しないことのほうに注意を向ける必要がある。
これは、結局、なんにも向上させてないんじゃないだろうか。
サッカーの選手たちが、強い海外のチームに参加したり、野球選手がメジャーリーグを目指したりするのは、そこに競争があるから、というよりも、向上できそうな環境があるからだと思う。
周りの仲間たちが強くて、強くなろうとしていて、憧れたり、悔しがったり、学んだり、教えたり、練習したりしている。そういう場を求めてそういう環境に行きたいと思うのではないだろうか。そこに競争の要素ももちろんあるけれど、重要なのは環境のほうなのだと、昨日のドジャースの大谷選手の活躍を見て考えた。彼はそういう場を求めて、日本のプロ野球からアメリカのメジャーリーグに行き、エンジェルスからドジャースに行ったのかもしれない。
向上できる環境の中では他人の失敗も発想も学びであると思う。競争ではなく、切磋琢磨という言葉の方がなんかしっくりくる。
いまやりはじめている作業センターふじなみの椎茸培養環境の向上により、質の良い椎茸がたくさん採れることを願っている。


作業センターふじなみ
地域で社会で生きていくって(平湯の家体験)
2024年09月18日
ふ




 作業センターふじなみでは、仕事の合間にも皆さんが楽しめるような様々な体験、活動を用意しています。
作業センターふじなみでは、仕事の合間にも皆さんが楽しめるような様々な体験、活動を用意しています。
今回は社会体験の一環として行っている年に一度の楽しみ。平湯の家への一泊旅行について紹介します。
めひの野園では、岐阜県の平湯温泉に社会体験ができる施設を持っていて、そこに様々な事業所の利用者の方々が行き、一緒にご飯を作ったり、温泉に入ったり、布団を敷いて寝たり、ゆっくり過ごしながらも特別な体験をするのです。
県外旅行やイベントなども大変嬉しい楽しみなのですが、皆さんはこの平湯の家で過ごすひとときを楽しみにしています。
ただ職員と一緒にカップラーメンを作るとか、温泉の熱さに驚き、水を足してちょうど良い湯加減を感じるとか、ホットプレートを使って自分で焼肉を焼いてみるとか、焼けるのを待つとか。そんな私たちにとって些細なことでも、とても非日常の楽しさや発見、驚きやみんなと過ごす安心など言葉では言い表せない体験をしていることになるんだなと。
ここでの体験で社会的なルールを覚えたりすることも大切なことですが、レトルトのカレーがぐつぐつ煮える様子を物珍しそうに見つめていたり、一緒に食事の机を拭いたり、玄関を掃いたり、スーパーに買い出しに行ったり、花火を職員、利用者の皆さん並んでじっーとぼっーと見つめてみたり。
ひとつひとつの体験からいろんな様子やその人のことが見えてきます。
こういった体験の積み重ねでたくさんの興味や意欲が湧いてきて新しい環境、機会にチャレンジしていく土台になったら良いなー
そんなひとときでした。
みんなと関わり、過ごす。
あたりまえの暮らしってどんなものなのかを知らないとイメージもできないし、恐れも消えない。
こういった素敵な施設を持っていることがちょっぴりめひの野園の職員として誇りに思ったりします。
皆さん良い顔してますね✨✨
作業センターふじなみ
ラジオに出演してきました!
2024年07月18日
 先日、めひの野園と作業センターふじなみの取り組みについてFMとやま様に取り上げて頂きました。
先日、めひの野園と作業センターふじなみの取り組みについてFMとやま様に取り上げて頂きました。
7/16 16:30からのヨリミチトソラのコーナーです。radikoというアプリで聞くこともできるので、もしよろしければ聞いてみてください。
大変貴重な時間を頂けたこと感謝です。
FMとやま様 ありがとうございました。
内容といえば、昔のめひの野園のあゆみや、その目的まで園長にたくさん聞いておいたおかげでしっかり伝えることができたのかなと思います。
自閉症の方に合った〇〇
自閉症の方にとって良いと思った〇〇
その内発的な動機こそ大事な歴史なんだなと、話してきて大変考えさせられました。
もっとみんなにこの取り組みというところも大事なことではありますが。
知られない、知らないことが不安や違いを生むという意味では、こういった取り組みがなぜできたのかという核心を話す機会がもっと増えれば良いなと思いました。
まずは、触れ合う機会、そのために知るということを続けていかなければと思いました。
ラジオパーソナリティの方、何度かラジオに出演させてもらいましたが、それぞれ素晴らしいアセスメント能力、しかも、即興で。
これぞ実は福祉に必要なチカラだったりして
しっかり、対象となる人が何を求めているのか、どう自分はサポートするのかできるのかを明確に迅速にされている姿を見て、皆さんプロだなーと。
そして、メディアに出て、地域に出て、たくさんの人と障害のある人の縁を作る。
そういったソーシャルワークの視点を職員が大事にすることを学んだ気がしました。
ケアワークは基本にしつつ、ソーシャルワークとはもしかしたらこういうこともかと、他分野の良いところを吸収する姿勢を共有できたらなと思います。
みんなで大事に育てたプレゼントが美味しく届けられますように。
作業センターふじなみ
ふじなみがラジオで取り上げられました
2024年06月13日


 投稿が少し遅くなりましたが、6月に入り作業センターふじなみは利用者さんたちがフル回転して頑張ってくれているおかげでたくさん良い椎茸、キクラゲがとれています。
投稿が少し遅くなりましたが、6月に入り作業センターふじなみは利用者さんたちがフル回転して頑張ってくれているおかげでたくさん良い椎茸、キクラゲがとれています。
先日、富山シティエフエム様、KNBラジオ様に作業センターふじなみの活動や新しく始めた菌床生キクラゲのことを取り上げて頂きました。
事業所の様子だけではなく、福祉のこと、障害福祉や地域福祉のことについて話を広げて頂けたことが大変嬉しく、この機会を通じてめひの野園の取り組みや障害のある方への理解が少しでも広がればと思います。
スタジオに行ってお話をさせてもらう上で、事前に園長から開所当初の話を聞いたり、改めて自分で私たちのやっていること、富山県の現状は他県と比べどんなだろうかなど様々な事を確認することがありました。
それがこの仕事をする上でとても大切な作業になるだろうと思い、緊張したけどやってよかったとも感じ。
よく言うソーシャルワークというのは、原点はそういうこと。
仕掛け人になり、輪を広げることなのかなと思ってみたり。
先輩方がやってこられたことや障害のある方々が、制度が整ってなかったときから支援者と一緒に寄り添って作り上げたものを後世に残していくことも大事なことで、そのためにどんどんメディアの方々からお力添えを受けることは必要だなと感じました。
とにかくめひの野園の仕事は全てがこの方にとって合う作業はこれかなと挑戦した結果のもの。
困っている障害のある人にこんなことがあればを形にした結果だということを話せてよかったなと思った緊張のラジオとなりました。
そして、そこで紹介してもらえた新しい事業の菌床の生キクラゲ。
改めて、ご紹介すると、焼きそば、餃子といろんなバリエーションがあります✨
焼きそばは、混ぜ合わせ前に醤油とマヨネーズで炒めてからの一手間があるとご飯が止まりません🤩
餃子は写真のこの細かさが大切!!
これを焼いてポン酢で食べる!
是非、ご賞味あれ✨✨
作業センターふじなみ
福祉の資格をとること
2024年03月16日
めひの野園の職員は福祉の資格を入職後に頑張ってとる人が結構います。
作業センターふじなみでは、実は春から社会福祉士の資格を持ったものが4人いることになるらしいのですが、その大半が仕事についてから資格を取得しています。
しいたけ栽培を通じて、障がいのある方の働くを支援しているわけですが資格の意義についてふと考えてみました。
それというのも、ある利用者の方にこの前こんなことを言われたからです。
「〇〇さん(職員)は社会福祉士持っとるから私のことなんでもわかっとるね!頭良い資格だし!」
そう言われたとき、私はこの資格をとってどんなことが利用者の方にしてあげられるのかとはっとさせられました。
その場で、
今までの経験、知識や関わりの中から彼らの障害特性は理解していることもあるし、サービスもわかる。
ただ、彼らが望むことをしっかり提供できるのか、この資格があるから?となると心の中で答えることはできませんでした。
でも、彼らにとってはこの資格が、ある意味目印になっているのかもしれないと。とても深く考えるきっかけになりました。
じゃあ、結局資格とはなんなのか?
勉強して頑張ってとる意味はなんなのか?
それは資格の合格はスタートラインで、その合格に向かうまで勉強した時間や知識を利用してさらに自分の支援している彼らに質の高い支援をすることで彼らの暮らしをより良いものにすることなのかなと。
資格をとっただけで障害特性や自閉症の支援が急に上手くなるわけはないのだ。
そのための勉強というのは終わりがないし、その下地があるから自分たちの福祉がどんな位置にあるかをわかるんだと。
めひの野園でそれってどんなことなのか。
その利用者の方に後日、「めひの野園で1番嬉しいことは何?」と聞いてみた。
すると、「ようわからんけど、自分の部屋があることかなー、誰も入ってこんし、ずっとゆっくり寝とれるわ。」と返ってきた。ここに至るまでいろいろな施設にいたことがあるということを本人から聞いて、そこでは自分だけの部屋はなかったと言われた。
私ははっとした。いろいろな行事や楽しいことを提供したり、いろいろな人との関わりもあるのに、その利用者が1番良かったことは当たり前にひとりひとり個室があることで、めひの野園の環境で、そこでゆっくり誰にも邪魔されず寝れることだった。これはめひの野園にとってとても誇れることであるが、普通の暮らしとしたら当たり前こと。それぞれに個室がある暮らし。それを気づくということは案外今の福祉においては難しいものなのかもしれない。
こんなことについて、最近はつらつらと考えては悩み、利用者の後ろ姿をじっーと見つめる。作業センターふじなみでは今年の春からまた何ができるのだろうか?
資格を持つ私たちが彼らに支援をする意味。
地域の人を巻き込んで、支援の質を向上させて、技術を使って彼らの見えにくい本当の想いを聞き、まだ障がいのことを知らない人にも理解を深めてもらう仕掛けをして最大の理解者になってもらったり。今年度行ったオープンファクトリーはその足掛かりになるように思う。地域や保護者の方の切実な悩みを聞いてここがあるよと安心してもらう。
これを継続していきながらさらに発展させることで、彼らが地域で当たり前の暮らしができて満足できるような、そんな支援をしていきたい。
新たな報酬改定もあり、その内容を見るといかに支援の質というものが問われているのかと思わされずにはいられない。
そのことを理解するために、頑張ってとった資格というものは決して無駄にはならない。あとはそこからがスタートだということを忘れないように来年度に臨みたい作業センターふじなみの一職員なのでした。